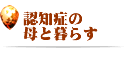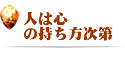|
 |
 |
 |
 |
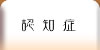 |
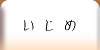 |
 |
 |
 |
 |
 |
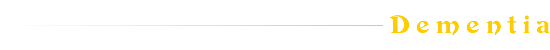 |

 |
|
 |
 |
 |
高齢化と共に増えている、認知症と介護の問題。 |
 |
|
| 認知症の母と暮らす |
 |
「ねえ、泰子。わし、お父っちゃんの顔忘れてしもうたから、何か写真でも部屋に貼ってもらえんけ?」 ある日のこと、部屋に入ると母が遠慮がちに私に言った。 心構えはしてきたつもりだったが、やはりショックだった。 母は毎日見ている私の顔でさえ、時折私の叔母と間違える。 しかし、しばらくすると元に戻り、またしばらくするとひどく記憶が混乱する。 認知症とは不思議な病気だ。 母には何を言っても忘れてしまうから、叱っても説教しても効果がない。 例えば、母は私が出張のために鞄に荷物を詰め込んでも、その中身を元の場所に戻す。 私はそれを咎めるが、そんなことは忘れて何度も同じことを繰り返す。 私の父は、いわゆる“寝たきり”で、介護度5に認定されていたが、認知症にはなっていなかった。 私の目には、動けなくとも記憶がシッカリしていた父の方が幸せに見えた。 そんなことを思ってしまうほど、母の症状は深刻だ。 |
 |
|
| 人は心の持ち方次第 |
 |
母と言い争ったあとは、とても気持ちが沈む。 病気のせいだと解かっているつもりだが、それでも私は母の言葉に傷つく。 そんなある時、私はふと主人から聞いた話を思い出した。 「徳川家康は織田信長に、妻と長男を殺せと命令された。その命に背けば攻め滅ぼされてしまうから、家康は家を守るために妻と長男を死なせたんだ。今の社会に、そこまでの苦しみはなかなかないだろう?我々は贅沢に生きてるんだよ。求めてはキリがない。」 主人は歴史書が好きで、そこから得た考え方などを私に教えてくれる。 時に私は自分の目の前のことだけにとらわれ、一歩引いて見てみれば小さな障害であっても、まるで世界の終わりのように感じている。 悩んだ時は、心が向いている角度を少し変えればいい。 |
 |
|
| 著書「喪われていく『母』の物語」 |
 |
価 格:¥1,680 (税込) 発 行:(株)文芸社 初 版:2009年10月15日 初 刷:2009年10月15日 −帯書き− 娘の夫の顔を忘れるほどに認知症が進んだ母。 混乱した母と言い争うたびに心を襲う猛烈な罪の意識と自己嫌悪。 しかし、そんな母の来し方をたどれば、そこには多くの知恵と子供たちへの深い愛情があった。 すべてが喪われてしまう前に、たくさんの思い出と記憶を留めたくて、これまでの日々を綴った。 ──願わくはその記録が、人々が日々を生きるためのヒントにならんことを祈って。 −推薦文− 認知症患者の介護話だと聞くと、たいへん重苦しいものに感じる。 しかし本書は、著者の母親が元気に働いていた当時の話などが本書全体の半分くらいを占め、私は本書を読むうちに、貧しくも活気があった時代を感じて前向きな気分にさせられた。 「私はいい時代に生まれた。電化製品のない時代を知っていて、十代の頃から電気洗濯機やら冷蔵庫やらテレビやらが家に入ってきて、生活がどんどん便利になっていった。あの新鮮な感激を味わった世代だからね」 ここに、「ありがたいこっちゃ」が口癖だという著者の母親と、著者の性格が見て取れる。 そんな著者が傷つき涙するのだから、自分の母親が認知症になりその側にいることが想像を絶する苦難であることがうかがい知れる。 悲しくも愛しい存在。
|

 |
|